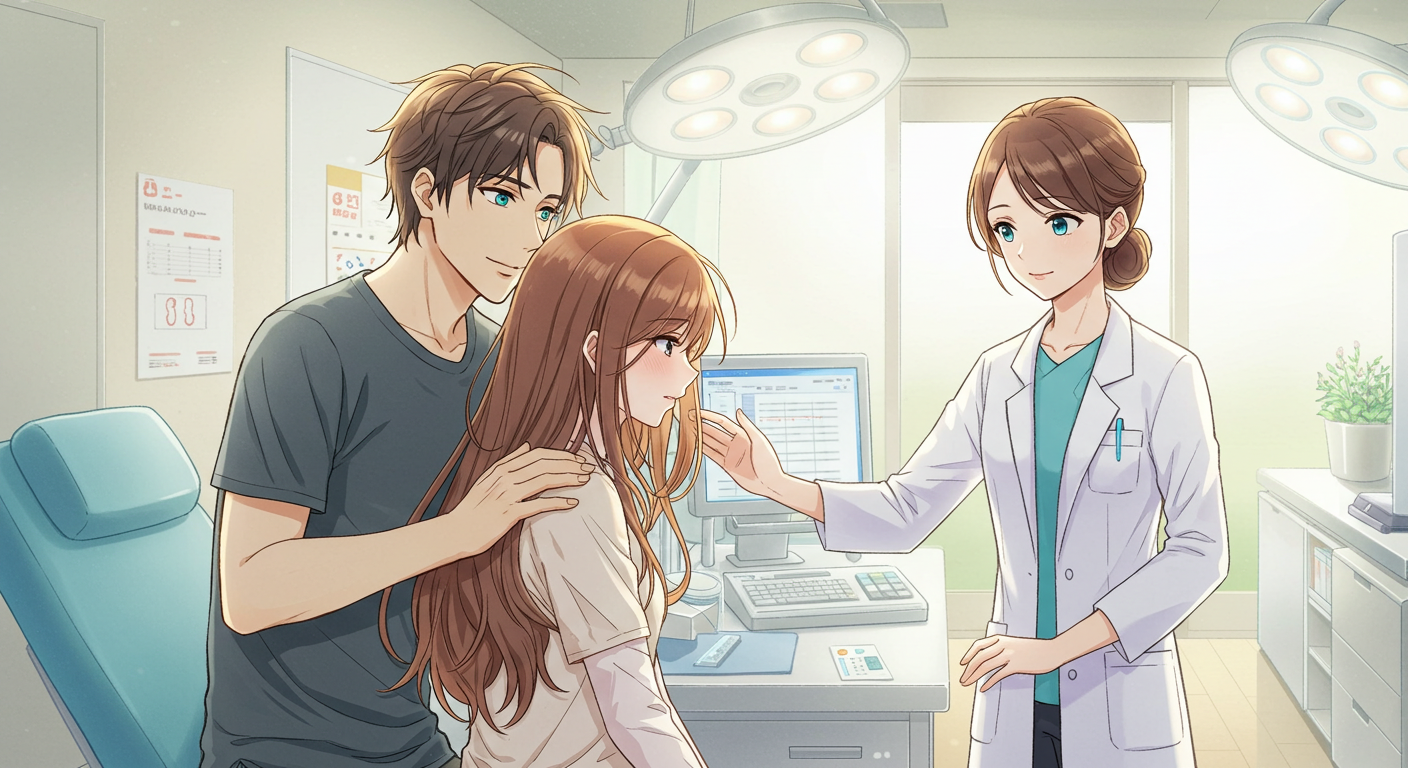不妊治療を始める前に知っておきたい基礎知識
妊娠を希望しているのに、なかなか子どもを授かることができない――そんな悩みを抱えるカップルにとって、「不妊治療」は重要な選択肢のひとつです。近年では医療の進歩により、多くの夫婦が不妊治療を受けて望む妊娠・出産に至っています。本記事では、不妊治療の基本的な内容から治療方法、費用、さらには公的な助成制度まで詳しく解説します。
不妊の定義とは?
「不妊」とは、避妊をせずに1年間性生活を続けても妊娠しない状態を指します。日本産科婦人科学会の定義に基づくと、以下のように分類されます。
- 一次性不妊:一度も妊娠したことがない
- 二次性不妊:過去に妊娠・出産の経験があるが、その後妊娠しない
不妊は女性だけでなく、男性にも原因がある場合があり、カップルでの検査・治療が重要です。
主な不妊治療の流れと種類
不妊治療は、段階的にステップアップしていくのが一般的です。以下は代表的な治療方法の紹介です。
1. タイミング法
排卵日を予測し、妊娠の確率が高い日に性交を行う方法。自然妊娠の延長線上にあり、副作用の心配も少ないのが特徴です。
2. 排卵誘発法(薬物療法)
排卵障害がある女性に対して、ホルモン剤を使って排卵を促す治療です。副作用として多胎妊娠や卵巣過剰刺激症候群が起こる可能性があります。
3. 人工授精(AIH)
精子を子宮内に注入し、受精をサポートする治療法。タイミング法や排卵誘発法で効果が見られない場合に行われます。
4. 体外受精(IVF)
卵子と精子を体外で受精させ、受精卵(胚)を子宮に戻す高度生殖医療です。比較的成功率が高い反面、費用や身体への負担が大きくなります。
5. 顕微授精(ICSI)
精子の運動性や数に問題がある場合に、1個の精子を卵子に直接注入する方法です。男性不妊に特化した治療として注目されています。
不妊治療の費用と保険適用
2022年4月から、不妊治療の多くが公的医療保険の対象となり、自己負担額が大幅に軽減されました。保険適用の対象になるのは以下の治療です:
- 一般不妊治療(タイミング法、排卵誘発法など)
- 人工授精(条件付き)
- 体外受精・顕微授精(年齢や治療回数に制限あり)
自己負担は原則3割で、1回あたりの治療費用の目安は以下の通りです。
| 治療方法 | 自費診療時の費用 | 保険適用後の目安(3割負担) |
|---|---|---|
| タイミング法 | 5,000〜10,000円 | 約2,000〜3,000円 |
| 人工授精 | 10,000〜30,000円 | 約3,000〜9,000円 |
| 体外受精 | 30万〜50万円 | 約10万〜15万円 |
| 顕微授精 | 40万〜60万円 | 約12万〜18万円 |
不妊治療に使える助成金・支援制度
東京都の主な支援制度
1. 不妊検査等助成金
- 対象:不妊検査を受けたカップル
- 上限:5万円
- 回数:1回限り
- 条件:東京都内に住民登録があること
2. 先進医療費助成金
- 対象:保険適用の特定不妊治療と併用して先進医療を受けた場合
- 上限:1回15万円
- 回数:年齢に応じて上限あり(39歳以下は最大6回)
不妊治療を受ける前に意識すべきこと
年齢による妊娠のしやすさの変化
一般的に、女性の妊娠率は30代後半から急激に低下し、40歳を超えると体外受精でも成功率は10〜20%程度になります。早めの検査・相談がカギです。
男性側の検査も必須
不妊原因の約半数は男性側にあるともいわれています。精液検査など、男性の検査も積極的に受けることが大切です。
クリニック選びのポイント
- 実績(成功率)や口コミ
- 医師との相性
- 通いやすさ(立地・診療時間)
- 治療方針の明確さ
まとめ|不妊治療は夫婦で支え合って進めることが大切
不妊治療は、身体的にも精神的にも、そして経済的にも負担のかかるものです。しかし、国や自治体の支援制度が整備されつつある現在、以前よりも安心して治療を受けられる環境が整ってきています。
「不妊かもしれない…」と感じたら、まずは婦人科や不妊治療専門のクリニックで検査を受けることから始めましょう。そして、パートナーとしっかり話し合い、治療方針を一緒に考えることが、後悔のない選択につながります。